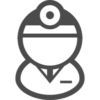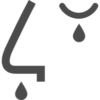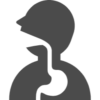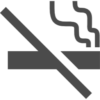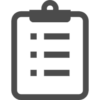以前から、食塩(ナトリウム)の摂取を減らし、野菜や果物(カリウム)を増やすことが血圧の改善に効果的であることが知られています。
日本人の平均的な塩分摂取量は約10gとされていますが、男性は7.5g未満、女性は6.5g未満への減量が望ましいとされています。さらに、高血圧の方でより厳しい目標を目指せる場合は、6g未満が理想的とされています。
具体的な食事改善の方法として、日本高血圧学会が作成した「ナトカリ手帳」(1)の内容を参考に、以下の方法をおすすめします。
食塩(ナトリウム)を減らす方法
・めん類の汁やスープを残す:全部残すと2~3gの減塩になります。
・漬物は控えめに:少量にとどめるか、食塩が少ない漬物を選びましょう。
・みそ汁は1日1杯以内に:具だくさんにして汁の量を減らすのがおすすめ。特に具を野菜にすると、カリウムの摂取にもつながります。
・味見をしてから調味料をかける:必要に応じて、少しずつ加えましょう。
・塩分の少ない調味料を使う:ポン酢、ケチャップ、マヨネーズ、ドレッシングなどが該当します。
・酢や香辛料を活用する:酢、こしょう、カレー粉、唐辛子、からし、ごまなどを使って風味を引き立てましょう。
・香りの強い野菜を取り入れる:しょうが、にんにく、ねぎ、しそ、三つ葉、みょうが、セロリ、山椒、ハーブなどが効果的です。
・少しずつ出るしょうゆさしを使う:1滴ずつ出せるタイプやスプレータイプの活用がおすすめです。
・塩味の多い加工食品や惣菜を控える:練り物、ハム、ソーセージなどには食塩が多く含まれます。
・食卓に調味料を置かない:手元にあると、つい使いすぎてしまいます。
・料理は適温で食べる:熱い料理は熱いうちに、冷たい料理は冷たいうちに食べましょう。
・普通の味と薄味を組み合わせる:すべてを薄味にせず、1品だけしっかり味付けして、献立にメリハリをつけましょう。
カリウムを増やす方法
・毎食、野菜を取り入れる
・野菜の付け合わせは残さず食べる
・果物を2日に1回は食べる
・1日2回以上、主食・主菜・副菜のそろった食事をとる
・100%果汁や野菜ジュースを飲む(※食塩や砂糖が添加されていないものを選ぶ)
・牛乳を飲む
・お茶、コーヒー、紅茶を飲む
※ 腎機能が低下している方、透析中の方、または血液中のカリウム値が上昇しやすい薬を内服している方などは、カリウムの摂取を制限したほうがよい場合があります。
これらの実践状況を確認する方法として、「尿ナトリウム/カリウム比(尿ナトカリ比)」の測定があります。 正式には尿を4回以上採取し、平均値を算出することが推奨されています。しかし、複数回の採取が難しい場合には、午前9時頃の尿(朝起きて2回目の尿)での検査も、やむをえない選択肢とされています。
なお、足利市では2025年度より、「おりひめ検診」の事後指導の一環として、推定1日食塩摂取量が10g以上で腎機能障害のない方を対象に、尿ナトカリ比の測定を開始しました。
尿ナトカリ比の目標値は以下の通りです(2):
・2未満:至適目標
・4未満:実現可能目標
これらの数値を上回っている場合は、現在の食生活を見直し、食塩を減らしたり、野菜や果物を増やしたりすることが望まれます。
1. 日本高血圧学会. ナトカリ手帳(第3版). 東京:厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課; 2023. 4-21.
2. T. Hisamatsu, M Kogure, Y Tabara, et al. Practical use and target value of urine sodium-to-potassium ratio in assessment of hypertension risk for Japanese: Consensus Statement by the Japanese Society of Hypertension Working Group on Urine Sodium-to-Potassium Ratio. Hypertension Research. 2024; 47(12): 3288-3302